![]()
稲荷社文楽座跡は、大阪市中央区博労町にある。
難波神社の御堂筋側に次の石碑が建立されている。
(東面)
稲荷社文楽座跡
(南面)
初代植村文楽軒の人形芝居は 文化八年(一八一一)ここ稲荷社に芝居を移し
その後中断したが 明治四年(一八七一)まで続き 文楽軒の芝居とも呼ばれ
文楽の名の起こりとなった
(西面)
昭和五十一年三月 大阪市 建之
また、難波神社の境内には、次の案内板がある。
難波神社と文楽
植村文楽軒が当社境内に人形浄るりの小屋を開いたのは、文化8年(1811年)のことで
その後一時移転、安政3年(1856年)再び当地に復帰した頃から「文楽軒の芝居」と呼ばれるようになった。
明治5年三世文楽軒の時に新開地の九条に移ったが、
17年に三味線の二代目豊沢団平を擁する「彦六座」が当社北門に開場して人気を集めたため、
文楽軒も近くの御霊神社境内に小屋を移して対抗した。
「彦六座」は明治31年団平が舞台で倒れたため解散、小屋は「稲荷座」としていろいろな興行に利用されたが、同45年取りこわされた。
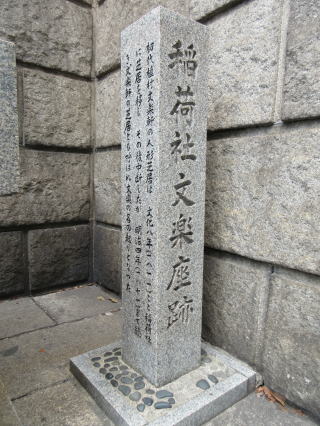
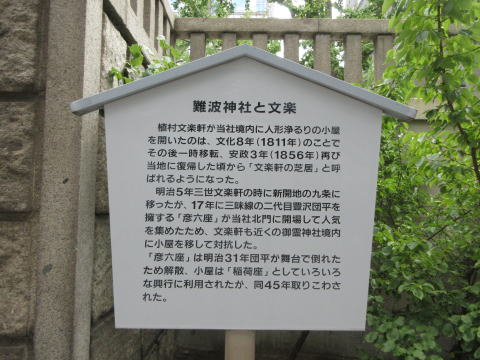
TOP PAGE 観光カレンダー
TOP PAGE 观光最佳时期