![]()
紫式部歌碑は、滋賀県野洲市あやめ浜にある。
石碑には次のように刻されている。
(南面)
おいつ島
しまもる神や
いさむらん
浪もさわがぬ
わらわべの浦
(北面)
沖の島は、古くから人の心をとらえていた島で、
歌に詠まれたり、文学の中にその名をとどめている。
この歌は、紫式部が、沖の島の対岸であるあやめ新田童子が浦のこの地から、
遠く沖の島を望んで詠んだものと言われている。
平成五年三月吉日建立
中主町観光協会
平成十六年十月合併により改名
野洲市観光物産協会
この歌は紫式部集に載せられており、次のように紹介されている。
みづうみに、おいつ島(注1)といふ洲崎に向ひて、
わらわべの浦(注2)といふ入海(いりうみ)(注3)のをかしきを、口ずさみに
おいつ島 島守る神や いさむらむ
波も騒がぬ わらはべの浦
(おいつ島を守っている神様が、静かにするようにいさめたのだろうか、
わらわべの浦は波も立たずきれいだこと)
「おいつ島」に老いを、「わらわべの浦」に童を思って趣向したものである。
紫式部が、父とともに越前に出向いて、その帰路に詠んだ歌である。
(注1)延喜式によると、蒲生郡に奥津島(おいつしま)神社がある。
現在、近江八幡市北津田町にある大島奥津嶋がそれだとすると、当地周辺の洲崎をいうものと考えられる。
(注2)現在地は不明であるが、大中之湖の東北方にある乙女浜かといわれる。「入海」は、入江のことである。
(新潮日本古典集成 「紫式部日記、紫式部集」 参照) → 紫式部ゆかりの地
野洲市観光ナビには、所在地の地図が掲載されている。
近江八幡市の百々神社にも、この歌の歌碑が建立されている。→ 百々神社 紫式部歌碑



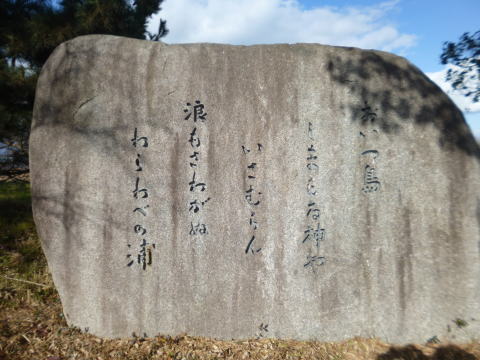
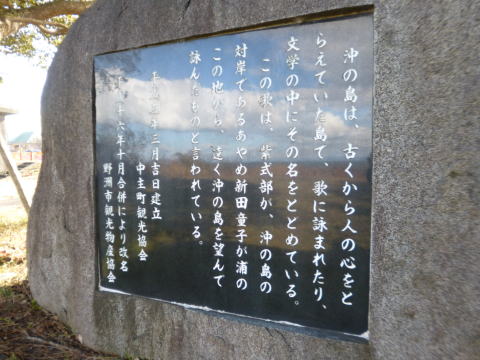
紫式部の越前往還の折りの和歌
新潮日本古典集成「紫式部日記 紫式部集」では、「紫式部の越前往還の折り」の和歌として、次のように紹介されている。
| 番号 | 原 文 | 現 代 語 訳 | 備 考 |
| 1 | 近江の海にて、三尾が崎といふ所に、 網引くを見て |
白髭神社 紫式部歌碑 |
|
| 三尾の海に 網引く民の てまもなく 立ち居につけて 都恋しも |
三尾が崎で網を引く漁民が、 手を休めるひまもなく、 立ったりしゃがんだりして 働いているのを見るにつけて、都が恋しい。 |
||
| 2 | また、磯の浜に、鶴の声々に鳴くを | ||
| 磯がくれ おなじ心に たづぞ鳴く なが思ひ出づる 人やたれぞも |
磯の浜のものかげで、 私と同じようにせつなさそうに鶴が鳴いている。 一体お前の思い出しているのは誰なのか。 |
||
| 3 | 夕立しぬべしとて、 空の曇りてひらめくに |
||
| かきくもり 夕立つ波の あらければ 浮きたる舟ぞ しづ心なき |
空一面が暗くなり、夕立を呼ぶ波が荒いので、 その波に浮いている舟は不安なことだ。 |
||
| 4 | 塩津山といふ道のいとしげきを、 賤(しず)の男(を)の あやしきさまどもして、 「なほからき道なりや」といふを聞きて |
||
| 知りぬらむ ゆききにならす 塩津山 よにふる道は からきものぞと |
お前たちもわかったでしょう。 いつも往き来して歩き馴れている塩津山も、 世渡りの道としてはつらいものだということが。 |
||
| 5 | みづうみに、おいつ島といふ洲崎に向ひて、 わらはべの浦といふ入海のをかしきを、 口ずさみに |
紫式部歌碑 (野洲市あやめ浜) 百々神社 紫式部歌碑 |
|
| おいつ島 島守る神や いさむらむ 波も騒がぬ わらはべの浦 |
おいつ島を守っている神様が、 静かにするよういさめたためだろうか、 わらわべの浦は波も立たずきれいだことよ |
TOP PAGE 観光カレンダー
TOP PAGE 观光最佳时期